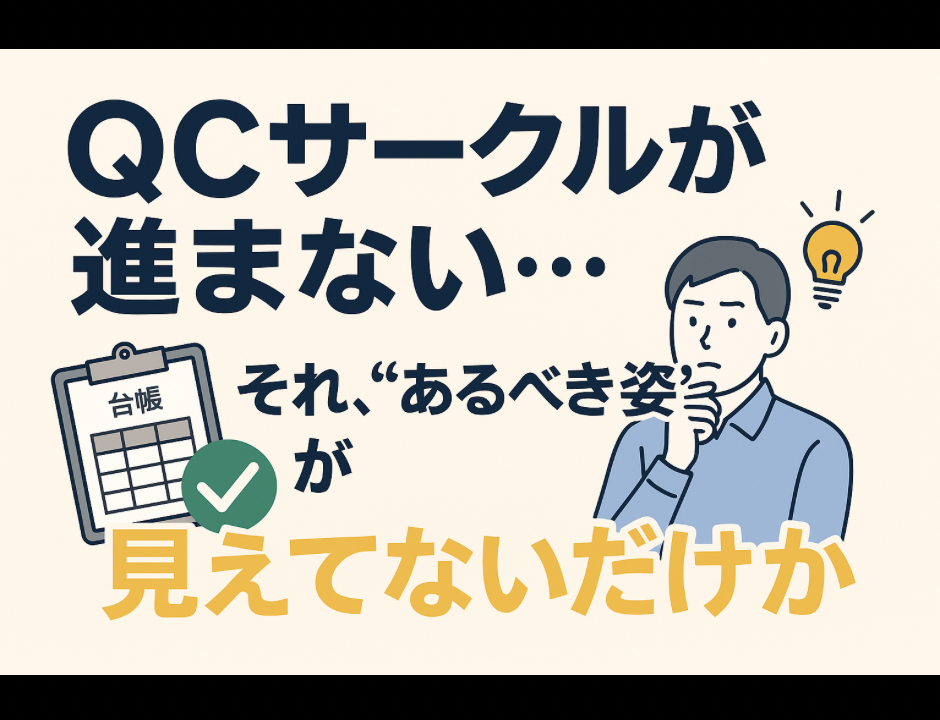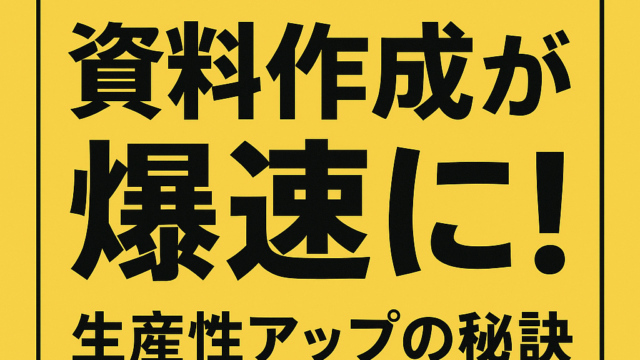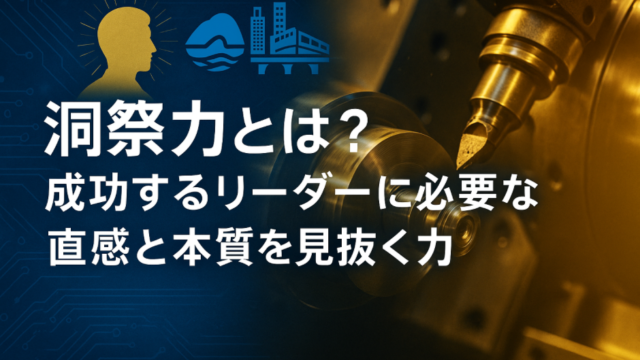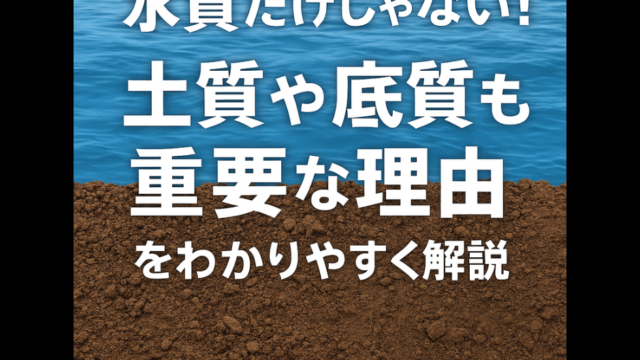QCサークルが進まない…それ、“あるべき姿”が見えてないだけかも
社内で刃物の発注管理を統一しようと、休止していたQCサークル活動を再開しました。「まずは共有の台帳を作って、全員で運用しよう!」と始めたのですが、いざ運用してみると予想外の壁にぶつかりました。
「何が問題なのか、よくわからない」
実際には、単価が更新されていなかったり、誰が入力すべきか曖昧だったりと小さな混乱はありました。でもそれを「明確な課題」として拾い上げることができない。「改善のためにやっているのに、改善すべき点が見えてこない」という、不思議な状況になっていたんです。
そこでふと気づいたのが、「あるべき姿(理想像)を定めていないから、問題点も見えてこないのでは?」という根本的な見落としでした。
あるべき姿がなければ、問題も見えない
QCサークルの基本的なステップに立ち返ると、「現状把握」と「目標設定」の間には、必ず“あるべき姿(理想像)”があります。しかし、自分たちはとにかく運用を始めてしまい、その「目指すゴール」が曖昧なまま進んでいました。
そのため、台帳を使っていても「これでいいのか?」「ここは直した方がいいのか?」という判断がつかない状態に。
理想像を定めて、ようやく見えてきた課題
そこで、「理想の状態は何か?」をチーム内で明文化してみました:
- 誰が見ても、発注状況・単価・在庫がすぐにわかる
- 単価は常に最新で、更新担当も明確
- 入力漏れやミスが出ない、シンプルな運用
このように“あるべき姿”を共有すると、現状とのギャップが見えてきました。単価更新のルールが未整備だったり、入力者によってフォーマットが違ったり。これまでは「なんとなく不便」と感じていたことが、「だから不便なんだ」と構造的に理解できるようになってきました。
メンバーからの意見を引き出す工夫
改善活動をチームで進めるには、メンバーからも率直な意見をもらう必要があります。けれど、「何か問題ありますか?」と聞いてもなかなか出てこないことも。
そのため、以下のような工夫をしました:
- 理想像を提示し、「現状と違うところは?」と具体的に聞く
- 匿名アンケートで意見を募集
- 「単価更新で困ったことは?」などテーマを絞る
- 否定せず、意見をくれたことに感謝する
QCサークルの“型”と現場の柔軟性のバランス
ふと、「この進め方ってQCサークルの型からズレてないか?」と疑問もわきました。でも大切なのは「型どおりにやること」ではなく、「現場にとって意味のある改善をすること」です。
QC活動のステップを意識しつつも、実情に合わせて柔軟に進める。この姿勢が、成果につながると感じています。
まとめ:課題は“理想とのギャップ”として見えてくる
今回の取り組みで実感したのは、問題が見えないときこそ「あるべき姿」が必要だということです。目標が定まっていないから、課題もはっきりしない。だからこそ、改善活動の第一歩として「理想像の明確化」はとても重要だと感じました。
QCサークルの再始動はまだ始まったばかりですが、これからもチームで意味ある改善を積み重ねていきたいと思います。