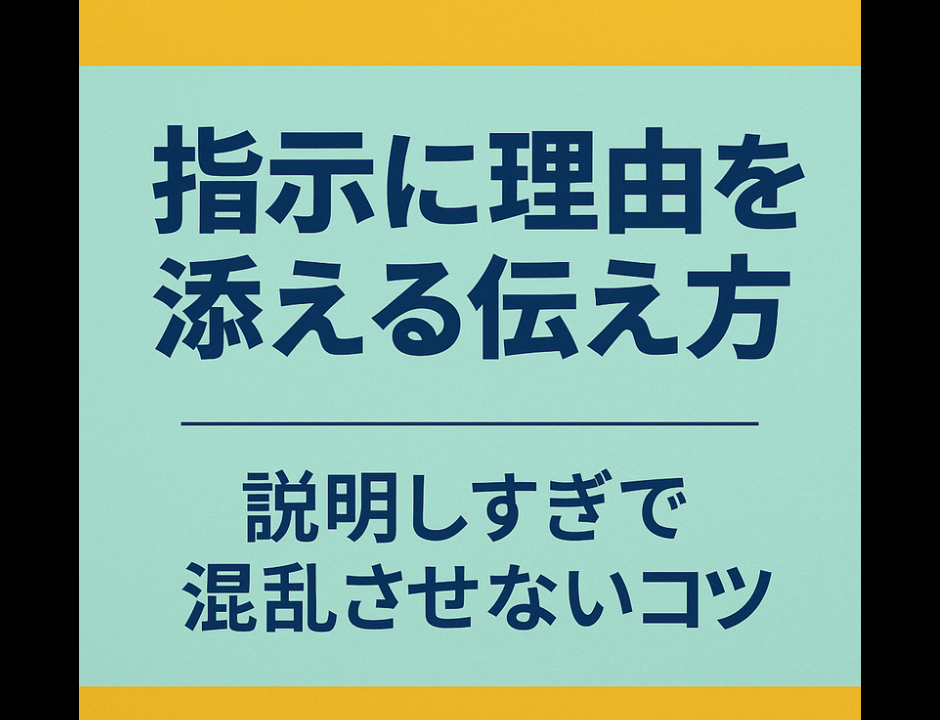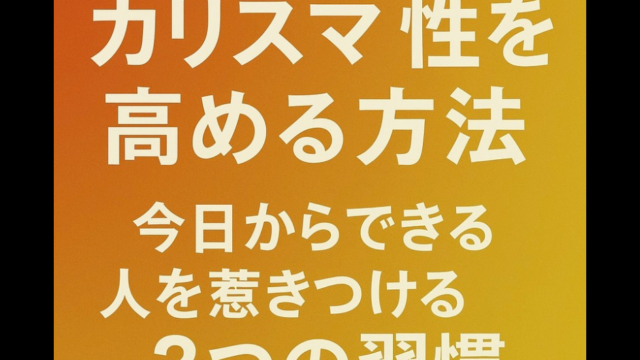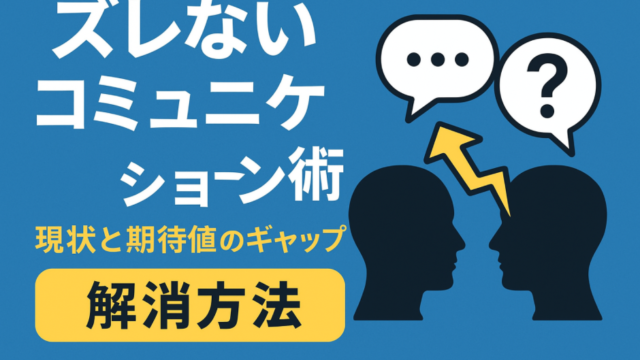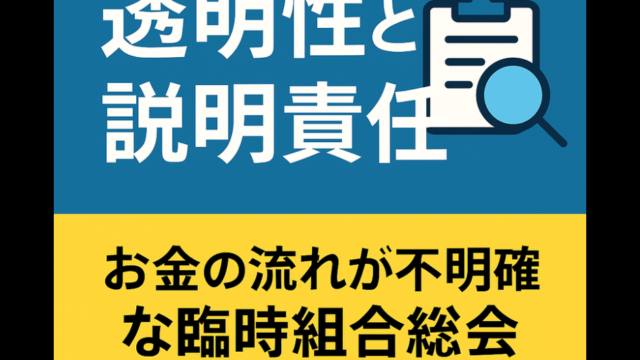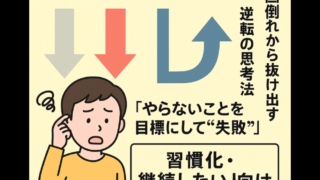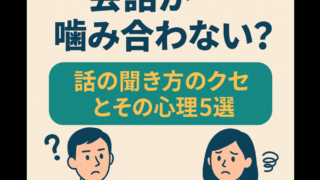Contents
指示に理由を添える伝え方|説明のしすぎで混乱させないコツ
よくある誤解:「全部を細かく説明しなければならない」
ある部下に「指示を出すときは理由を伝えて」と伝えたところ、背景や経緯をすべて詳細に話そうとするようになりました。
真面目な姿勢は評価できますが、実際には情報が多すぎると聞き手が混乱してしまうこともあります。
職場の実例:発注書の説明で不安が生まれたケース
たとえば朝礼で、次のような指示がありました。
刃物の価格が変動しているので、発注書を自分のところに持ってきてください。金額が違っていたら止めます。
この発言を聞いた人の中には、
- 「止められたら刃物が届かず、現場に支障が出るのでは?」
と不安に感じた人もいたかもしれません。
ポイントは「一言の補足」
この場合、以下のような一言を添えるだけで相手の不安は軽減されます。
価格確認のために一旦止めるけど、現場に影響が出ないようにこちらですぐ対応します。
このように、相手の疑問や不安を先読みして、必要なところだけを補足するのがコツです。
説明に必要なのは「量」ではなく「的確さ」
指示の目的は「全部を話すこと」ではなく、相手が迷わず動ける状態をつくることです。
伝え方のポイントは以下の通りです:
- 全部を説明する必要はない
- 相手が分かっていそうなことは省略する
- 不安に感じそうなことは一言で補足する
まとめ:「伝える力」は“相手目線”で磨かれる
説明は100%話すのではなく、相手の頭に疑問が残らない「ちょうどよい量」で伝えるのが理想です。
必要なのは、“相手が何を知りたがっているか”を想像して、そこだけを押さえて伝える力です。
たくさん話すより、要点を絞って伝えたほうが、相手にとっては分かりやすく、動きやすくなります。
職場でのコミュニケーションに悩んでいる方は、ぜひ「説明は相手目線で考える」ことを意識してみてください。