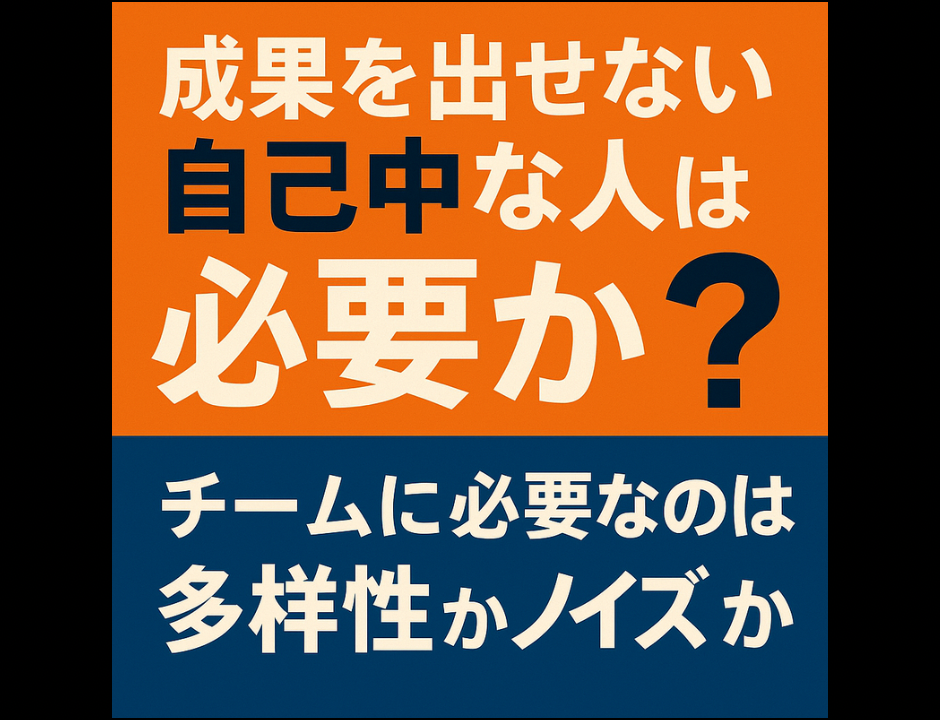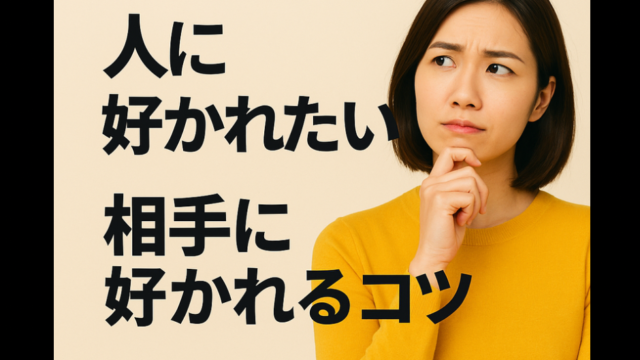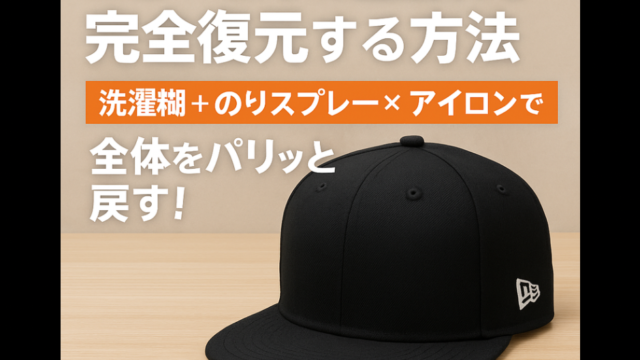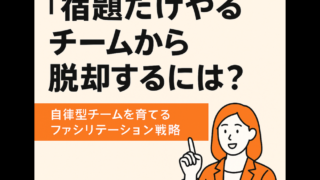成果を出せない自己中な人はチームに必要か?職場の多様性との向き合い方
「いろんなタイプがいた方がチームは強くなる」は本当?
組織論では「チームは多様性がある方が強くなる」と言われます。確かに、異なる視点や経験を持つメンバーが集まれば、相乗効果が生まれる可能性はあります。
しかし現場で感じるのは、すべての「違うタイプ」が歓迎されるわけではないという現実です。特に、
- 自己中心的で空気が読めない
- 他人視点をまったく持たない
- 成果を出していない
こういったタイプの人がいると、チームがまとまりにくくなり、むしろ弱体化してしまうと感じます。
「成果を出せない自己中タイプ」がなぜ職場で浮いてしまうのか
自己中心的な人は、ビッグファイブ性格特性で言えば「協調性が低く、誠実性も低い」傾向にあります。その結果、
- 報連相がズレている
- 責任感が希薄でトラブルに発展しやすい
- 周囲との信頼関係が築けない
問題は、こうした人ほど「自分に問題がある」とは思っていないことです。むしろ「自分が正しい」「周囲が無駄にこだわっている」と思っているケースもあります。
多様性は大切、でも「機能する多様性」であることが前提
私自身、多様性を否定するつもりはありません。違った価値観が集まることで、新しい発想やブレークスルーが生まれることもあるでしょう。
しかしそれは、
最低限の協調性や誠実性があり、成果を出す意欲がある人に限った話です。協力も成長もせず、周囲に負担をかけるだけの存在は「多様性」ではなく「ノイズ」となってしまいます。
「その人がいる意味」を冷静に見直すことも必要
成果も出さず、チームに悪影響を与える人材を「多様性だから」と容認し続けることは、結果的に組織全体の士気やパフォーマンスを下げる原因になります。
「この人がいない方がチームがスムーズに回るのでは?」という直感は、多くの場合、現場の正直な判断です。無理に“育てよう”としすぎることが逆効果になることもあるでしょう。
まとめ:扱いにくい自己中タイプはチームに必要か?
自己中な特性を持つ人でも、突出したスキルや成果を出せるならば受け入れられる余地はあります。
しかし、「協調せず、成長せず、成果も出せない」場合は、チームにとって明確なマイナスです。
多様性は「機能してこそ価値がある」。現場目線での冷静な判断こそが、チームを強くするのだと私は思います。