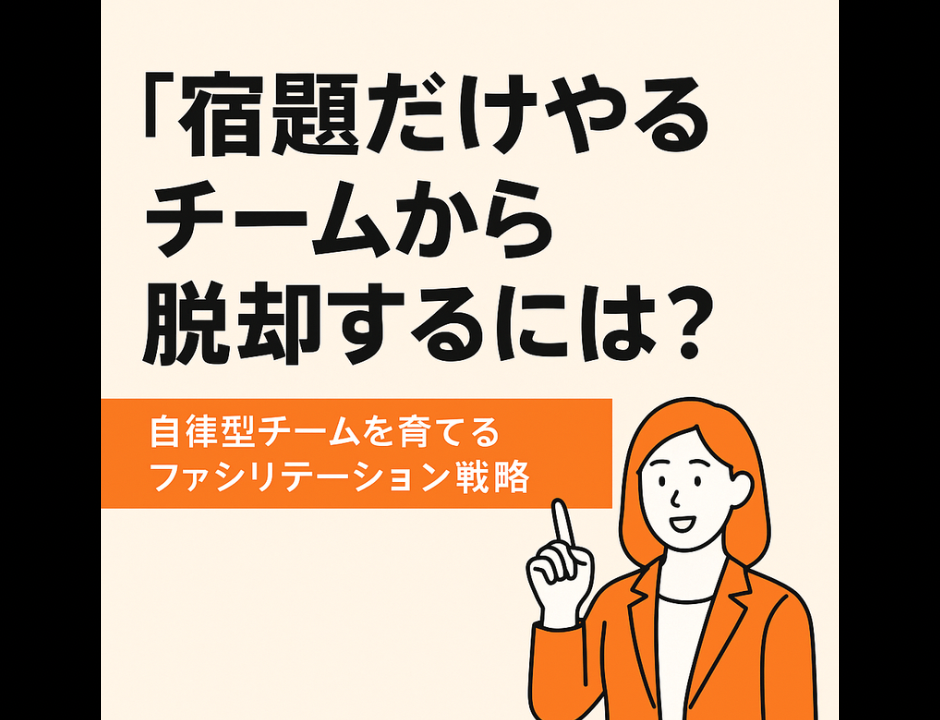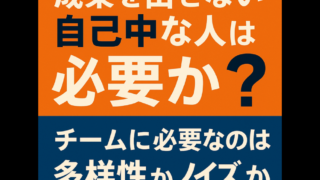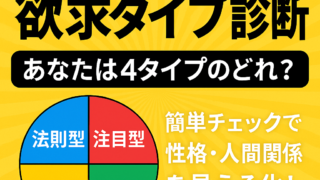Contents
宿題だけやるチームからの脱却方法|自律型チームを育てるファシリテーション戦略
なぜ「宿題だけやればいい」と思ってしまうのか?
日本の学校教育では、教師が出した課題(宿題)をこなすことが評価基準となってきました。この経験から、社会人になっても以下のような行動パターンが定着しがちです:
- 指示されたことだけやる
- それ以上の行動はしない
- 評価は“出された課題をこなしたかどうか”で決まる
この無意識のパターンが、チームに「思考停止」を引き起こしているのです。
宿題依存から脱却する4つのアプローチ
① 宿題の役割を「最低限の準備」と再定義する
宿題は目的ではなく、あくまで“気づき”や“思考の起点”です。「宿題だけでは不十分」というメッセージを明確に伝えましょう。
② アクションをチームで自発的に設定する
ファシリテーションの最後に、「次回までに何を実行するか?」をメンバー自身が話し合って決める時間を設けます。
宿題=共通タスク、アクション=主体的タスクという役割分担が有効です。
③ 成果共有の仕組みを取り入れる
次回のファシリテーションでは、宿題に加え「自主的なアクションの報告」を必須にしましょう。こうすることで、宿題だけでは評価されない空気が生まれます。
④ 小さな成功を可視化し称賛する
どんなに小さな一歩でも、それを取り上げ、チーム内で称賛しましょう。これが自発的行動の継続的な動機づけになります。
まとめ|ファシリテーターが設計を変えればチームは変わる
「宿題しかやらない」チームは意欲がないのではなく、過去の学習経験に縛られているだけかもしれません。
大切なのは、ファシリテーターが環境を整え、行動を引き出すデザインをすること。宿題は“きっかけ”にすぎず、本当に価値を生むのは「自分たちで決めて、動いたこと」です。