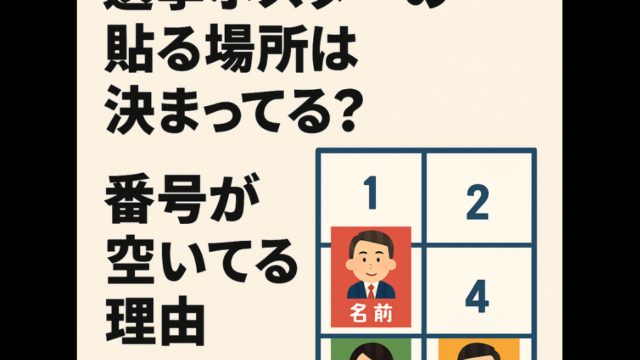訓読みがない漢字もある!音読み・訓読みの違いをわかりやすく解説
音読みと訓読みのおさらい
訓読み(日本語の読み方)
もともと日本語にあった言葉に漢字をあてはめたもの。
例:山(やま)、川(かわ)、走る(はしる)、高い(たかい)
👉 漢字がなくても日本語として意味が通じます。
音読み(中国の読み方)
「音読み」は “おんよみ” と読みます。
これは、中国から伝わった発音をそのまま日本に取り入れた読み方 だからです。
つまり、音読み“おんよみ”=中国読み(“おとよみ”と読まないから)と覚えるとわかりやすいです。
例:学(ガク)、校(コウ)、電(デン)、話(ワ)
👉 音だけでは日本語らしく聞こえませんが、二字熟語で意味が通じます(例:学校、電話)。
訓読みがない漢字
中国由来の概念をそのまま表した漢字は、日本語の対応語がなかったため、音読みしかない のです。
- 棒(ボウ) … 鉄棒(てつぼう)
- 率(リツ) … 比率(ひりつ)
- 秒(ビョウ) … 秒針(びょうしん)
- 胃(イ) … 胃腸(いちょう)
- 距(キョ) … 距離(きょり)
音読みがない漢字(国字)
逆に、日本で新しく作られた「国字(こくじ)」には、音読みが存在しない漢字 もあります。
- 畑(はたけ)
- 峠(とうげ)
- 辻(つじ)
- 鰯(いわし)
- 栃(とち)
まとめ
- 音読み=中国読み(中国から来た発音)
- 訓読み=日本語読み(日本語として昔からある言葉)
- 訓読みがない漢字 … 棒、率、秒 など
- 音読みがない漢字 … 畑、峠、辻 など
漢字の成り立ちを知ると、「どうしてこの読み方なんだろう?」という疑問もスッキリします。身の回りの漢字を見て、「これは音読み?訓読み?」と考えてみると、もっと漢字が楽しくなりますよ!