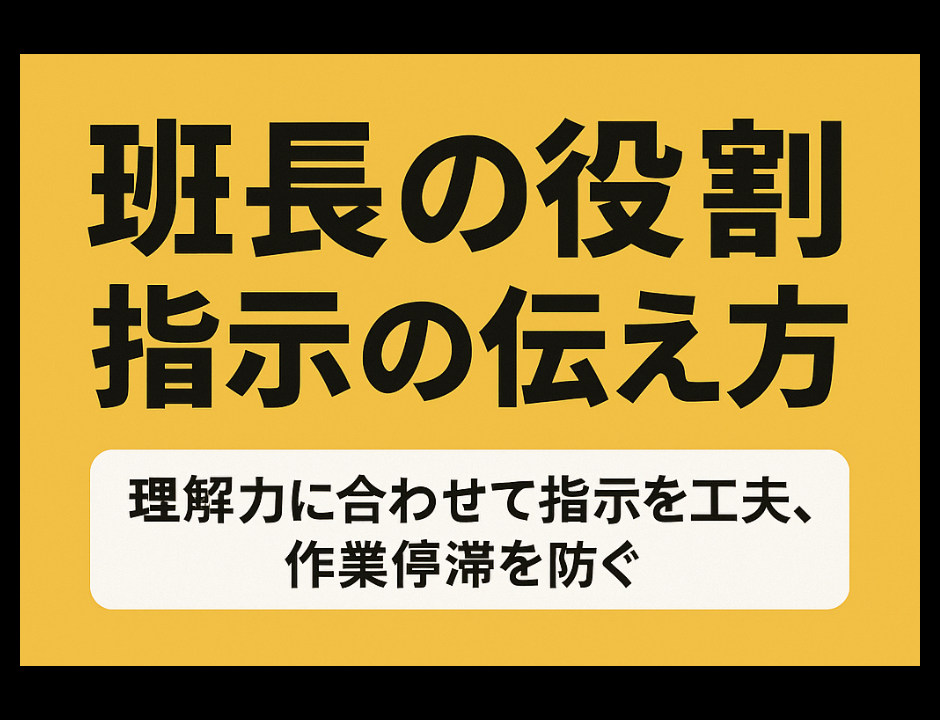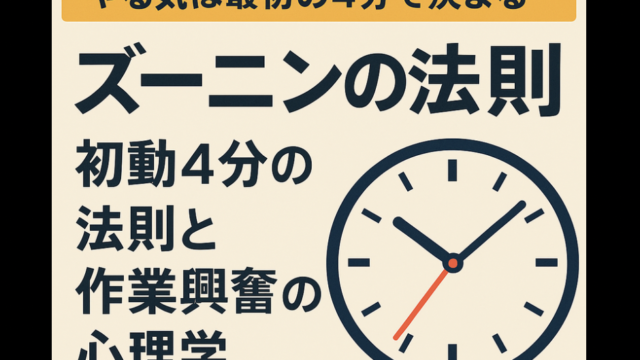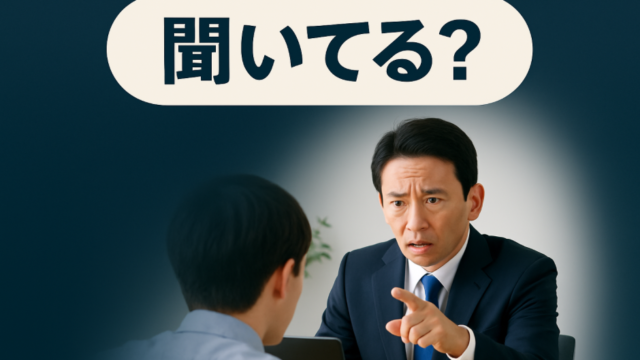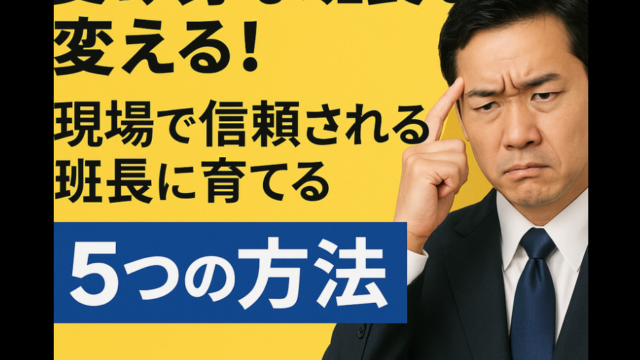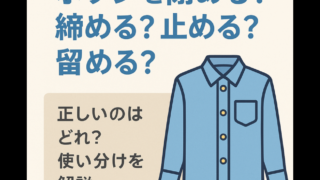Contents
【指示の伝え方】「伝書鳩」から卒業するリーダーの実践術— 担当者に合わせて内容を変える具体例とチェックリスト
「上司の指示をそのまま伝えているのに、現場が動かない…」――その理由は、担当者に合わせた“指示の設計”が抜けているからかもしれません。
なぜ“そのまま伝える”では動かないのか
上司の言葉をそのまま届けるだけでは、担当者が理解できずに手が止まることがあります。これは俗に「伝書鳩」状態。主な原因は以下の通りです。
- 担当者の経験・スキルレベルがそれぞれ違う
- 同じ言葉でも、人によって理解の深さが異なる
- 背景や目的がわからないと、自分で判断して動けない
リーダーの役割:指示の「再設計」
リーダー(班長)の役割は伝言ではなく、再設計です。つまり、同じ上司の指示であっても、担当者によって「伝える内容」そのものを変える必要があります。
具体的なやり方(4ステップ)
① 自分が意図を理解し、腹落ちする
まずは指示の目的・狙い・期待アウトカムを自分の言葉で説明できるように。曖昧なら上位者に確認してから現場へ。
② 担当者に合わせてタスクを分ける
習熟度に応じて作業を小分けに。例えば全体10件の作業を2件ずつ任せ、短サイクルで完了とフィードバックを回すと迷いが減ります。これはリーダーの腕の見せ所で、作業者の能力把握が前提です。
③ 背景と優先順位を補足する
「なぜ今これをやるのか」「どこまでできればOKか」「締切・品質の基準は?」をセットで示すと、担当者が自律的に判断しやすくなります。
④ 進捗を確認し、完了まで伴走する
渡した仕事の進み具合を確認し、困っている点があればサポート。そのうえで完了まで導くのがリーダーの役割です。最初は短い間隔で、安定してきたら頻度を調整しましょう。
今日から使えるチェックリスト
- 指示の「目的/期待アウトカム/期限/品質基準」を自分の言葉で言えるか
- 担当者の習熟度に合わせてタスクを分割したか(例:2件ずつの小分け)
- 背景・優先順位・判断基準を補足したか
- 進捗確認のタイミング(いつ・どの粒度で)を合意したか
- 「迷ったらここに戻る」連絡経路を明確にしたか
よくある質問(FAQ)
Q. どの担当者にも同じ指示書を配れば効率的では?
A. 標準指示はベースとして有効ですが、理解力・経験値に合わせた補助を重ねることで初めて現場は止まらなくなります。
Q. タスクの小分けは甘やかしになりませんか?
A. 小分けは学習カーブを設計する手段です。早い成功体験を積み、確度が上がれば粒度を大きくして自走を促します。
Q. 進捗確認の頻度は?
A. 立ち上がりは短サイクル、安定後に延伸。品質×納期リスクで頻度を決めるのがコツです。
まとめ:伝え方を変えれば、チームが動く
- 「そのまま伝える」はNG。担当者によって内容を変えるのが基本
- 小分け・背景説明・進捗伴走で停滞と手戻りを削減
- リーダーの価値は指示の再設計にある