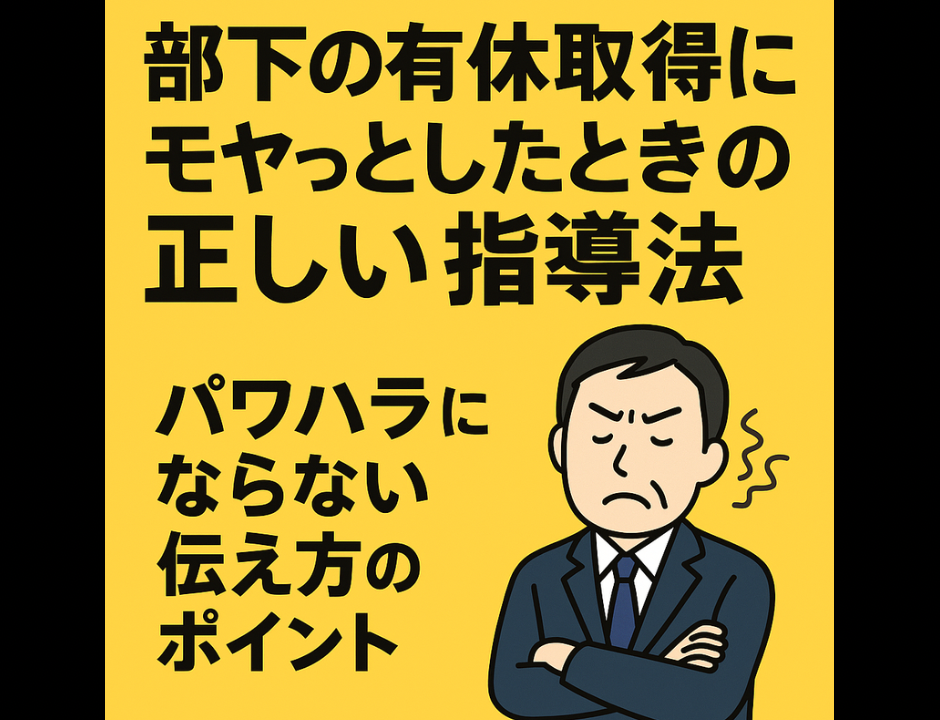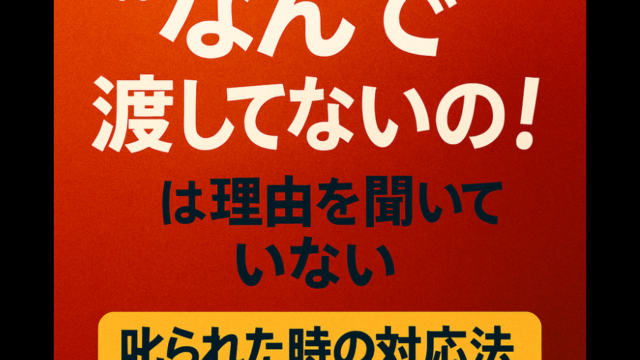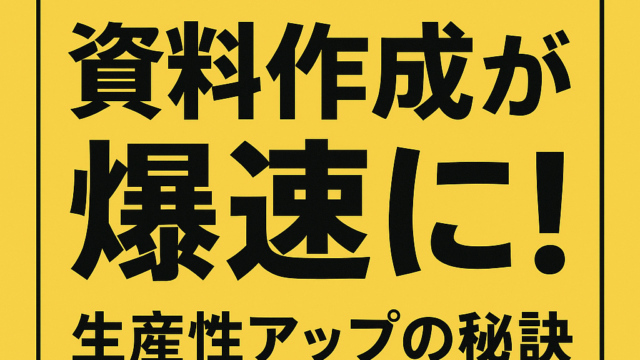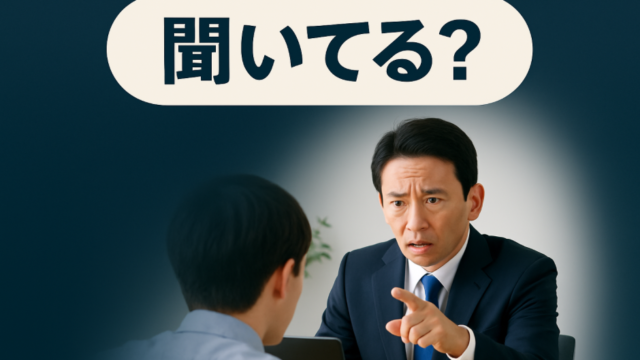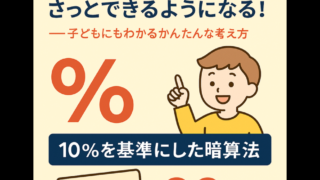Contents
有休指導の実例:部下にどう伝えればパワハラにならないか【文例あり】
月に1回の有休取得を推奨する会社方針のもと、部下が先月に子育てによる有休を2回取得。今月も「仕事が薄いので休みたい」と申し出があったが、報告ルートが班長止まりで係長に報告がない──。このケースに対して行った指導文と、「パワハラにならない伝え方」を具体的にまとめる。
状況整理(結論を先に)
- 会社方針:月1回の有休取得を推奨
- 部下の実績:先月、子どもの看病で有休2回
- 現在:通常業務は薄いが教育期間中
- 問題点:係長(あなた)への報告なし/「今休みたい」と申し出
実際に伝えた指導(LINEで送った原文)
【指導内容】 ① 報告ルートについて 有休の取得は係長に報告すべき内容。 今後は必ず係長へ報告すること。 ② 仕事に対する考え方 先月2回休んでいることも踏まえ、 今月は“休むこと”を考えるのではなく、 手が空いているこのタイミングで 「自分に何ができるか」「何を学ぶか」を優先して考えること。 ③ 有休の取得について 子育て中という家庭環境を踏まえ、 有休は権利であるが、 取得のタイミングや優先順位を考え、 必要な時に使えるよう計画的に取得すること。 (例:もしかしたら来週、休まないといけない状況になるかもしれない等を考慮する)
なぜこの指導がパワハラに当たらないか
重要なのは「事実に基づいた業務上の指導」である点。以下のポイントで説明する。
- 事実ベース:報告経路の不備や休暇の頻度など客観的な事実に基づいている。
- 人格否定がない:「〜しろ」「〜できない」といった人格攻撃や侮辱表現を避けている。
- 権利を否定していない:有休を「権利」と明記しつつ、取得の仕方・タイミングを指導している。
- 目的が明確:懲罰目的ではなく、業務の安定と本人の成長を狙った指導である。
LINEで送るときの実務的な注意(必須)
- 必ず1対1で送る(グループ送信や公開はNG)。
- 語調は淡々と。絵文字・感嘆符・過度な強調は避ける。
- 送信記録を残す(メモ:送った日時・目的)。
- 送信後、反応が強ければ対面でフォローする(説明の場を作る)。
上司が気をつけるべき「伝え方のコツ」
- 導入で意図を明示する:「業務上の指導として伝える」一言を添える。
- 質問ではなく行動指示にする:曖昧な質問形式だと本人が逃げやすい。明確な期待値を示す。
- 感情を抜く:表現を客観化(例:「〜すること」)し、個人的な恨みがないことを示す。
- 面談の場を確保:LINE送付後、誤解がないかを確認する短い面談を設定する。
よくある質問(FAQ)
Q. 有休は権利なのに制限しても良いのか?
A. 有休そのものを制限することはできない。しかし、業務運営上の観点から「計画的に取得する」ことを求めるのは妥当であり、指導の範囲内。
Q. 伝えたあと、部下が泣いたり逆ギレしたら?
A. まずは落ち着いて面談で事情を聞く。感情が高ぶっている場合は、その場で深追いせず一旦時間を置くことも有効。記録は必ず残す。
まとめ(上司としての心構え)
今回の指導文は「事実・業務ルールに基づく」「権利を否定しない」「目的が改善」であり、適切に伝えればパワハラには当たらない。重要なのは文面だけでなく、送る場面・トーン・その後のフォローまで含めた対応だ。
参考:送る前に自分の感情をチェックし、「指導の目的」を改めて言語化しておくと、余計な感情が出にくくなる。
この記事は実例を元に一般化した内容であり、法的助言ではありません。個別の労務問題や複雑なケースは労務担当者や社労士に相談してください。