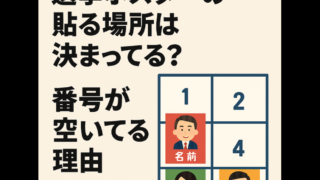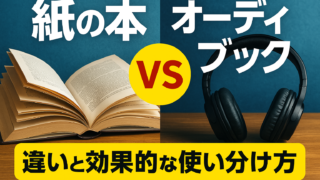技能検定は上司の責任か?機械加工技能士の育成で大切にしたい考え方
はじめに:技能検定と上司の関わり
毎年、機械加工技能士の技能検定を受けています。部下にも受験の機会があり、今年も何人かが挑戦予定です。その中でいつも悩むのが、上司としての関わり方です。
上司が合格を目指す?それとも自主性を重視?
① 合格させるのが上司の仕事という考え方
一部では「上司は部下を合格させるための計画・支援を行うべき」とされています。たとえば、過去問演習の実施や進捗管理などがこれにあたります。
たしかに、組織として技能レベルの底上げを図るには、有効な方法です。
ただし、やりすぎると「やらされ感」が強まり、本人の学びにつながりません。スキルアップの本質を見失う可能性があります。
② 自主性を重視するという考え方
一方で「技能検定は個人のキャリア開発。大人なのだから自分で進めるべき」という意見もあります。
自主性を尊重すれば、本当の意味で力をつけやすいという利点があります。
ただし、完全に任せきりにすると、結局やらない・間に合わないといった結果になることも多く、適度なサポートが必要です。
論語に学ぶ育成:「憤らせざれば啓せず」
私自身、部下を育てる立場になってから意識するようになった言葉があります。それが論語の「憤らせざれば啓せず(いきどおらせざればけいせず)」です。
意味は、「本人が知りたい・理解したいという気持ち(=憤り)を持たなければ、教えても真の理解にはならない」というものです。
技能検定も同じで、「自分の力で合格したい」と思ってこそ、学びが身になります。上司がやるべきことは、「火をつける環境を整える」ことだと考えています。
実践している上司としての関わり方
- 受験の目的と意義をしっかり伝える
- 必要な教材や演習機会を提供する
- 進捗管理は軽めに、あくまで相談ベースで
- 合格・不合格よりも「取り組みの姿勢」を評価する
これにより、部下は「やらされている」のではなく「自分の成長のためにやっている」と感じるようになります。
まとめ:育成に近道はない
技能検定の合格は確かに大切です。しかし、それはスキルアップの“通過点”であり、目的ではありません。
大切なのは、部下が自ら動き出すきっかけを作り、必要な支援をそっと差し伸べること。強制せず、でも放置しない。そのバランスこそが、上司としての真価だと感じています。