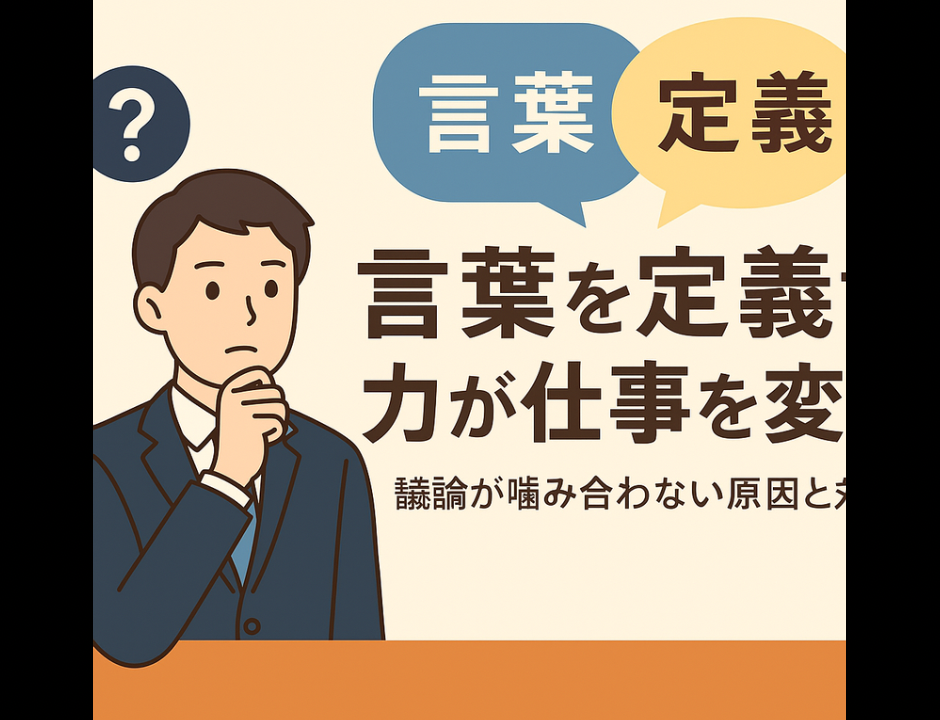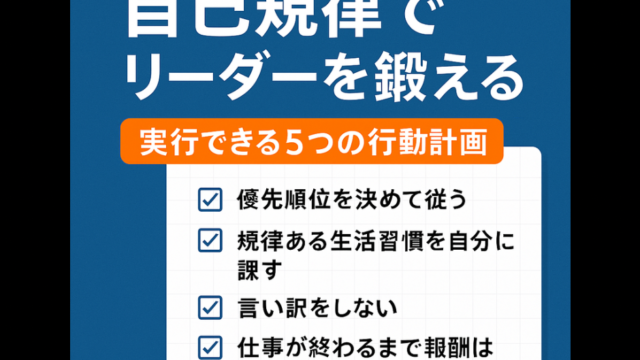Contents
言葉を定義する力が仕事を変える|議論が噛み合わない原因と対策
会議や打ち合わせ、日常のやり取りの中で「話が噛み合わない」「何かズレている」と感じたことはありませんか?その原因の多くは、実は言葉の定義が人によって異なることにあります。
今回は、私がかつて在籍していたコンサルティング会社での実体験をもとに、「言葉を定義することの重要性」と、それがどのように仕事の成果に影響するのかをご紹介します。
グループディスカッションで見えた“定義の力”
新卒採用の選考で行われていたグループディスカッションでは、以下のようなお題が出されました。
「日本の“笑”を世界に広めるにはどうしたらいいか?」
学生たちは様々な意見を出し合いますが、実はこの議題で最も評価されたのは、次のような発言ができた学生でした。
「まず、“日本の笑”や“世界”が何を指すのか定義しませんか?」
定義がズレていたらどうなる?
- 「日本の笑」=お笑い芸人の漫才
- 「日本の笑」=伝統芸能の落語
- 「世界」=欧米諸国
- 「世界」=アジア圏
このように定義がバラバラだと、出てくるアイデアも方向性が異なり、議論はかみ合いません。どれだけ良い提案をしても、そもそもの前提が違えば意味がないのです。
仕事でも“定義”がズレるとズレが起こる
これは学生の面接だけでなく、社会人の仕事の現場でも日常的に起きています。
よくあるすれ違いの例
- 「品質を上げて」→ 品質とは見た目?耐久性?納期?
- 「すぐやって」→ 今すぐ?今日中?明日まで?
- 「売上を伸ばす」→ 単価を上げる?件数を増やす?
こうしたズレは、信頼関係や成果物の精度に悪影響を与えます。
定義から始める人が評価される理由
言葉を定義できる人は、次のような力を持っていると見なされます。
- 議論の軸をつくる力
- 全体を俯瞰して捉える思考力
- 他者と共通認識を持つための配慮力
つまり、「仕事ができる人の土台」とも言える力なのです。
まとめ:仕事の出発点は「言葉の定義」
もし、議論や仕事の中で「話が進まない」「すれ違いが多い」と感じたら、ぜひ次のことを試してみてください。
- 話の中のキーワードを一度立ち止まって定義する
- 「私が言う○○とは、□□という意味です」と共有する
- 相手の定義も確認してズレをなくす
言葉を定義することは、すべての仕事や人間関係の基本です。
ぜひ日常のコミュニケーションでも意識してみてください。
この記事が役立った方は、ぜひSNSでシェアいただけると嬉しいです!
リンク