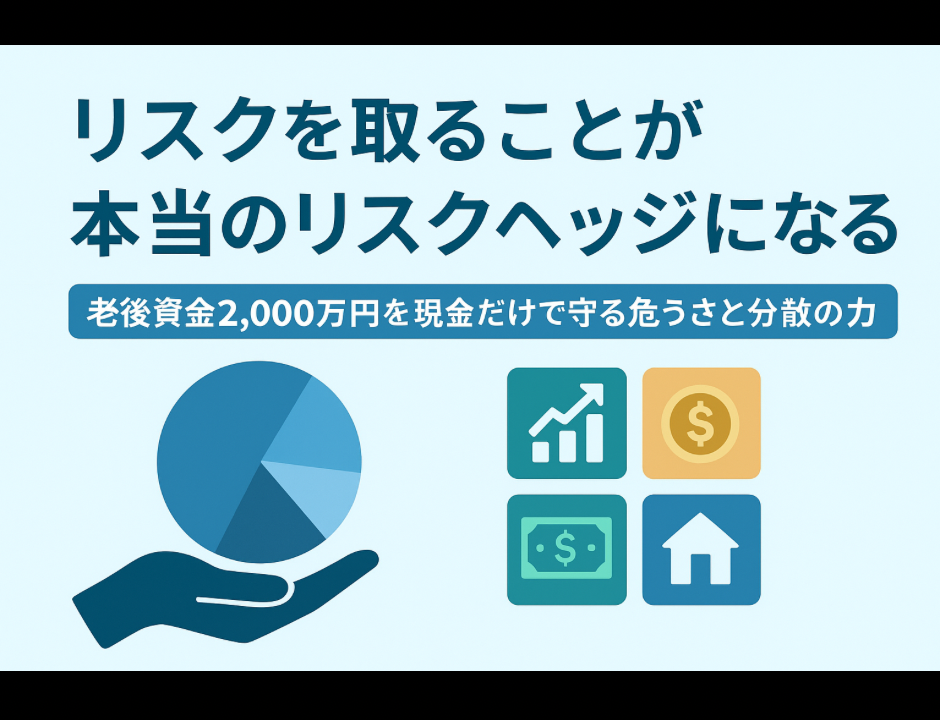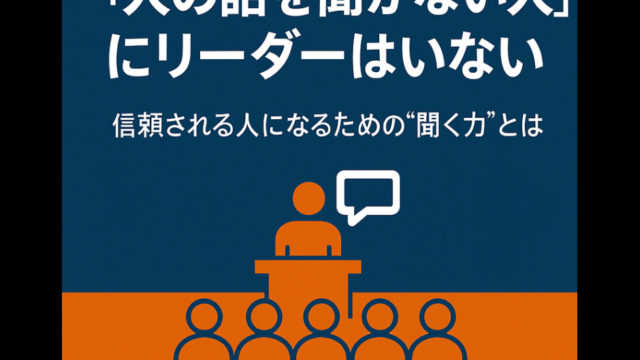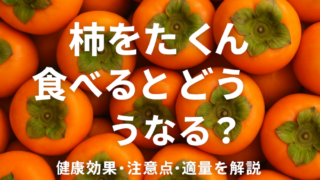Contents
リスクを取ることが本当のリスクヘッジになる— 老後資金2,000万円を現金だけで守る危うさと分散の力
「老後に2,000万円必要」といっても、それは“今の価値”。インフレ・為替・金利変動を考えると、現金だけで守ることはかえってリスクです。本記事では、なぜ“リスクを取ることがリスクヘッジになる”のか、その論理と実践ステップ(スタート地点の把握→ゴール設定→最適な資産配分)を具体的に解説します。
1. 現金だけを持つことがリスクである理由
「現金=安全」と直感的に思う人は多いですが、長期で見ると現金特有のリスクが存在します。
- インフレリスク: 物価が上がれば現金の実質価値は目減りします。
- 低金利リスク: 金利が低いと預金だけでは資産が増えません。
- 為替リスク(機会損失): 外貨の価値上昇の恩恵を受けられない。
つまり、将来の購買力(生活費・医療費など)を守るためには、現金以外の資産を検討する必要があります。
2. なぜ分散(ポートフォリオ)が資産防衛になるのか
株式・債券・外貨・不動産などに分散することで、
- 一つの資産が下落しても他の資産でカバーできる可能性が高まる
- インフレ・為替・利回りといった複数の要因に対応できる
- 長期ではリターンが期待できる資産を保有することで購買力を維持できる
要するに、「リスクを取る」こと自体が資産を守る手段になるのです。
3. ポートフォリオ最適化のための3ステップ
最適な配分を考えるには、順序が重要です。以下の3ステップを基本にしましょう。
ステップ A: 現在地を正しく把握する(スタート地点)
- 総資産・負債の把握
- 年収・可処分所得・毎月の貯蓄額
- 投資経験・リスク許容度(例:保守的/中立/積極的)
ステップ B: 目標(ゴール)を明確にする
ゴールが定まらなければ手段は決まりません。ゴール例:
- 60歳で老後資金3,000万円を確保したい
- 50歳でセミリタイアする
- 子どもの教育費を優先する
ゴールによって、リスク許容度や投資期間が変わり、結果的に最適なポートフォリオは変化します。
ステップ C: 手段(資産配分)を選ぶ
移動手段の比喩で言えば、目的地が決まって初めて「歩く(現金重視)」「自転車(債券重視)」「車(株式+債券)」などが選べます。代表的な配分例:
- 保守型:現金・債券70% / 株式20% / その他10%
- 中立型:現金・債券40% / 株式50% / その他10%
- 積極型:株式70% / 債券20% / 現金10%
(※比率はあくまで例。個別状況に合わせて調整してください。)
4. 具体例:為替で見たケーススタディ
例:1ドル=100円の時に10ドル(=1,000円)を保有→円安で1ドル=130円になれば同じ10ドルが1,300円になります。
このように外貨を持っているだけで、為替変動による評価益が得られる場合があります。
逆に為替が円高に向かえば評価損を受けるため、外貨だけに偏るのは避けるべきです。分散でリスクをコントロールしましょう。
5. よくある質問(FAQ)
- Q1: 現金を完全にゼロにしていいですか?
- A: いいえ。流動性確保のために生活費数ヶ月〜1年分の現金は確保すべきです。ただし余剰資金は運用で増やすことを検討しましょう。
- Q2: どのくらいの割合で外貨を持つべきですか?
- A: 個人の状況次第です。目安としては総資産の5〜20%を外貨・海外資産に割く投資家が多いですが、為替リスクを理解してから決めてください。
- Q3: 投資初心者はまず何をすべき?
- A: ①現在地把握 ②具体的なゴール設定 ③少額で分散(インデックス投資・積立)から始める、の順が安全です。
6. 次のアクション(今すぐできる3つのこと)
- 【今】総資産(預金・投資・負債)を一覧化する
- 【今週】老後の必要額・年齢などゴールを数字で決める(例:65歳で必要な生活費×年数)
- 【今月】少額からでも積立投資を始め、月次で振り返る
リンク